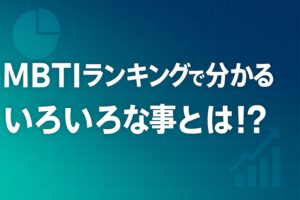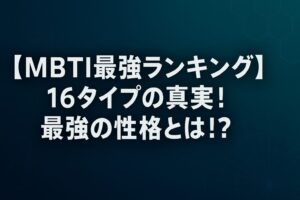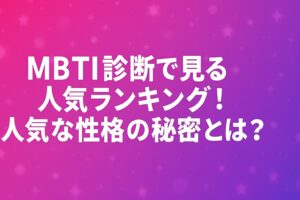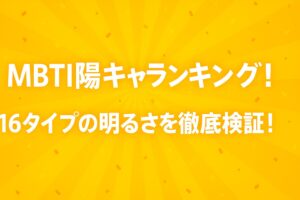MBTI診断を試したものの、「自分の性格タイプは日本人の中では珍しいのかな…」と感じたり、「周りと少し違う気がするけど、大丈夫だろうか…」と不安に思ったりしたことはありませんか。
自分の性格が多数派なのか少数派なのか、つい気になってしまうものですよね。
まずはこの記事を通して、日本におけるMBTIタイプの全体像を把握してみましょう。
ご自身の性格を客観的に見つめ直し、新たな自己理解を深めるきっかけにしてください。
この記事では、ご自身の性格タイプと日本人全体の傾向との関係性を知りたい方に向けて、
– 【2025年最新版】日本人に多いMBTIタイプランキング
– 上位にランクインした各性格タイプの詳しい特徴
– 自分のタイプを理解し、強みとして活かすためのヒント
上記について、解説しています。
ランキングの結果に一喜一憂する必要は全くありません。
大切なのは、自分自身のユニークな個性を知り、受け入れることです。
この記事が、自分らしさを見つけ、より豊かな人間関係を築くための一助となれば幸いです。
ぜひ参考にしてください。
MBTI診断とは何か?
MBTI診断とは、あなたの生まれ持った心の利き手、つまり本質的な好みや傾向を理解するための自己分析メソッドです。
巷で流行している性格占いや単なる適性検査とは一線を画し、心理学者のカール・グスタフ・ユングが提唱したタイプ論を基に開発された、世界的に信頼されている心理検査の一つになります。
これを受けることで、自分自身のことをより深く知り、自分らしく生きるための大きなヒントが得られるでしょう。
なぜこれほど多くの人がMBTI診断に惹かれるのでしょうか。
それは、複雑化する社会の中で、自分の強みや弱み、本当に大切にしたい価値観を客観的に把握したいというニーズが高まっているからです。
キャリアの選択や人間関係で悩んだ際に、自分という人間の「取扱説明書」のようなものが欲しくなる方もいるかもしれません。
MBTIは、そうした自己理解への欲求に応えてくれるツールなのです。
具体的には、4つの異なる指標(興味関心の方向、ものの見方、判断の仕方、外界への接し方)を用いて、あなたの生まれ持った心の使い方を明らかにします。
例えば、エネルギーの源が人との交流にあるのか、一人の時間にあるのかで「外向型(E)」か「内向型(I)」かが分かれる仕組みです。
この診断を通じて、自分に合ったコミュニケーションスタイルやストレスへの対処法、さらには適職探しのヒントまで見つけられます。
MBTIとエニアグラムの違い
MBTIとエニアグラムは、共に自己理解を深めるツールとして人気ですが、その成り立ちと診断の視点に大きな違いがあります。MBTIは、心理学者カール・ユングの理論を基に、人が外界をどう認識し、どう判断を下すかという「認知のプロセス」に着目した性格診断です。4つの指標を組み合わせて全16タイプに分類し、個人の思考の癖や強みを明らかにします。一方、エニアグラムは古代の知恵に起源を持つとされ、人が行動する際の根源的な「動機」や「囚われ」に焦点を当てるものです。9つの基本タイプで人格を捉え、自己成長の過程で直面する課題を示唆してくれるでしょう。つまり、MBTIは心の「機能」を、エニアグラムは心の「動機」を探るアプローチであり、両者を併用することで自己を多角的に理解することが可能となります。
MBTI診断の基本的な概要
MBTI診断は、個人の心の働きや興味の方向性を理解するための自己申告型性格検査で、正式には「マイヤーズ・ブリッグス・タイプ指標」と呼ばれます。この診断では、「エネルギーの方向(外向E/内向I)」「ものの見方(感覚S/直観N)」「判断の仕方(思考T/感情F)」「外界への接し方(判断J/知覚P)」という4つの指標から、個人の自然な心の使い方を明らかにします。それぞれの指標からいずれか一方のアルファベットが選ばれ、その組み合わせによってINFPやESTJといった合計16種類の性格タイプが導き出される仕組みです。日本では「16Personalities」という無料診断サイトが広く知られていますが、これは厳密なMBTIとは異なる理論も含むものの、手軽な自己分析ツールとして人気を博しています。診断結果は自己理解を深め、キャリア選択や人間関係の改善に役立つヒントを与えてくれるものであり、性格に優劣をつけるためのものではない点を理解しておくことが重要でしょう。
日本人に多いMBTIタイプランキング
それでは、日本人に多いMBTIタイプのランキングをご紹介します。
数ある性格タイプのなかでも、日本社会では特定のタイプが上位を占める傾向が見られるのです。
あなたの診断結果がランキングに入っているか、ぜひ確認してみてください。
このランキング結果には、日本の文化的な背景が深く関係していると考えられています。
協調性を大切にし、周囲と足並みをそろえることを美徳とする社会性が、特定の性格傾向を育みやすいのかもしれません。
真面目で献身的な姿勢が評価されやすい環境も、その一因でしょう。
では、具体的にどのタイプが上位にランクインしているのでしょうか。
以下で、ランキングトップ5の性格タイプを、それぞれの特徴とともに詳しく解説していきます。
1位:INFP(仲介者型)
日本のMBTIランキングにおいて、最も多くの割合を占めるのがINFP(仲介者型)です。その数、実に日本人口の約16.44%にも上ると言われており、およそ6人に1人が該当する計算になります。INFPは内向型(I)・直観型(N)・感情型(F)・知覚型(P)の4つの気質を併せ持ち、「情熱的な理想主義者」とも呼ばれるでしょう。普段は物静かで控えめな印象を与えるものの、心の内には強い信念と独自の価値観を秘めているのです。非常に高い共感力を持ち、他者の喜びや痛みを敏感に察知する繊細な心根が、その大きな特徴といえます。また、豊かな想像力と創造性を備えており、芸術的な分野で才能を発揮する人も少なくありません。周囲との調和を重んじ、相手を思いやる文化が根付く日本において、この利他的で心優しいINFPの気質が育まれやすいのかもしれません。
2位:ENFP(広報運動家型)
日本人に多いMBTIタイプランキングで第2位に位置するのがENFP(広報運動家型)になります。国内の統計によれば、その割合は約13.78%にも上り、7人に1人近くが該当する計算でしょう。ENFPは情熱的で好奇心が強く、人との繋がりを心から大切にする社交的な性格として知られます。持ち前の明るさと高いコミュニケーション能力で、周囲を自然と巻き込み、活気ある雰囲気を作り出す力を持っているのです。また、既成概念にとらわれず、次々と新しい可能性を見つけ出す創造性も大きな魅力といえます。一方で、自由を愛するあまり、計画的に物事を進めるのは少し苦手かもしれません。SNSでの自己表現が活発化し、多様な生き方が認められつつある現代日本の風潮が、ENFPの持つ特性とマッチしていると考えられます。
3位:INTP(論理学者型)
日本におけるMBTIのタイプ別人口で第3位に位置するのが、INTP(論理学者型)でした。ある調査によると、その割合は日本人全体の約10.96%にものぼり、およそ10人に1人がこのタイプに該当する計算になります。INTPは「論理学者」という呼び名の通り、尽きることのない知的好奇心を持ち、複雑な問題の分析や独自の理論構築に情熱を注ぐことでしょう。物事の本質を鋭く見抜く力に長けているのが大きな特徴。内向的(I)な性質から一人の時間を大切にし、静かな環境で思索にふけることを好む傾向が見られます。その独創性と分析能力は高く評価される一方で、論理を優先するあまり感情表現が不得手で、周囲からはクールでユニークな存在と見られるかもしれません。専門知識が活きる研究職やITエンジニアといった分野で、その才能を遺憾なく発揮していると考えられます。
4位:ISFJ(擁護者型)
日本人で4番目に多いとされるのが、ISFJ(擁護者型)であり、その割合は全人口の約8.1%を占めるといわれています。「擁護者」という名の通り、非常に献身的で思いやりが深い性格が際立つタイプです。周囲の人を助けることに大きな喜びを感じ、家族や友人、所属するコミュニティを大切にするでしょう。また、責任感が非常に強く、一度引き受けた仕事や役割は最後まで忠実にやり遂げる真面目さも持ち合わせています。伝統や社会的なルールを重んじ、安定した秩序のある環境を好む傾向が見られます。控えめで謙虚な人柄から、自ら率先して前に出るよりも、裏方として組織やチームを支える「縁の下の力持ち」のような存在になることが多いかもしれません。彼らの優れた観察力は、他者の感情の機微やニーズを敏感に察知することを可能にし、その温かい人柄から周囲に安心感を与え、厚い信頼を寄せられることでしょう。
5位:INFJ(提唱者型)
日本人に多いMBTIランキング、第5位はINFJ(提唱者型)です。世界的には全人口の1~2%未満とされる非常に希少なタイプですが、日本における割合は約6.5%前後と推定されており、グローバルな視点では比較的多いことがわかります。INFJは、内向(I)・直観(N)・感情(F)・判断(J)の4つの指標を併せ持つタイプ。物静かで控えめな印象を与えやすいものの、内面には確固たる信念や理想を秘めた情熱家の一面があるでしょう。人の感情や心の機微を敏感に察知する優れた共感能力を持ち、他者に深く寄り添うことができます。その一方で、自身の高い理想と現実との間で葛藤したり、他者の痛みを自分のことのように感じてしまったりする繊細さも持ち合わせているのです。世の中をより良く変えたいという強い思いを原動力に、粘り強く行動し続ける姿は、まさに「提唱者」の名にふさわしいと言えます。
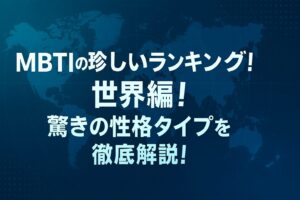
MBTI診断の活用と注意点
MBTI診断は、自己理解を深めたり他者とのコミュニケーションを円滑にしたりするための非常に便利なツールです。
しかし、その結果を絶対的なものとして捉えるのではなく、あくまで自分を知るための「きっかけ」として活用することが大切でしょう。
診断結果に一喜一憂するのではなく、自身の強みや課題を知るヒントとして受け止めるのが賢明な使い方と言えます。
その理由は、人の性格は非常に多面的であり、診断を受けた時の気分や置かれている状況によっても回答が変わりやすいからです。
MBTIは、人が生まれ持った「心の利き手」のような、自然な心の使い方や物事の捉え方の傾向を示すものに過ぎません。
この点を理解せずに結果を鵜呑みにすると、自分や他人を「〇〇タイプだから」と決めつけ、かえって人間関係に摩擦を生む原因にもなりかねないのです。
例えば、診断結果で「内向型(I)」と出たからといって、社交性が全くないわけではありません。
単に、一人で過ごす時間でエネルギーを充電しやすい傾向があるというだけです。
同様に「思考型(T)」の結果が出た方が、感情的な共感ができないわけでもありません。
このように結果を柔軟に解釈し、自己成長や他者理解のツールとしてポジティブに活用していくことが重要になります。
MBTIの活用方法
MBTIは自己理解を深め、他者との円滑な人間関係を築くための有効なツールとして活用できます。自身のタイプを知ることで、思考の癖や強み・弱みを客観的に把握できるでしょう。例えば、外向型(E)か内向型(I)かを知るだけでも、エネルギーをどこから得るかがわかり、自分に合った働き方やストレス解消法を見つけるヒントになるのです。キャリア選択においても、INFP(仲介者型)なら創造性を活かせる仕事、ESTJ(幹部型)なら組織をまとめる役割が向いているなど、適性を考える上で大きな材料となり得ます。また、チーム内での活用も効果的であり、異なるタイプのメンバーの価値観や意思決定プロセスを理解すれば、不要な衝突を避け、生産性を高めることにもつながるでしょう。株式会社リクルートマネジメントソリューションズのような企業でも、組織開発の研修にMBTIが導入されている事例があります。ただし、診断結果は絶対的なものではなく、あくまで自己分析の一助と捉える姿勢が大切です。
診断結果を直感で捉える
MBTIの診断結果は、自分を理解するための一つのヒントに過ぎません。例えば、日本人に多いとされるINFP(仲介者型)と診断されても、すべての特徴が自分に当てはまるとは限らないでしょう。診断結果のアルファベット4文字に自分を無理やり当てはめるのではなく、「自分にはこういう一面もあるのかもしれない」と直感的に捉えることが大切になるのです。そもそも診断は、その時の気分や状況で回答が変わる自己申告形式がほとんどであり、結果は絶対的なものではありません。そのため、診断結果はあくまで自己分析を深めるための参考資料として活用するのが賢明な判断といえます。書かれている16タイプの特徴の中から、しっくりくる部分だけを拾い読みするのも良い方法となります。診断は自分を縛るものではなく、新たな可能性に気づかせてくれるきっかけだと考えてください。
環境による変化を考慮する
MBTIの診断結果は、生涯にわたって不変というわけではありません。人の性格は、年齢、職業、ライフステージなどの環境要因に応じて、柔軟に変化しうるものなのです。例えば、学生時代には内向型(I)だった人が、人との交流が必須の営業職を数年経験することで、外向型(E)の側面が自然と養われるケースは珍しくないでしょう。また、20代の頃は論理的思考(T)を重視していた人も、管理職となり部下を育成する立場に変わることで、相手の感情に寄り添う力(F)が発達することも考えられます。こうした経験の積み重ねが自己認識に影響を与え、診断結果が変わるのはごく自然な現象です。そのため、「日本人に多いランキング」は現時点での傾向を示す一つの指標であり、自身の成長と共に結果が変わり得る可能性を理解しておくことが大切になります。
日本と世界のMBTIタイプ比較
日本のMBTIタイプ分布は、世界全体と比較すると非常にユニークな特徴を持っています。
あなたが当たり前だと感じている周囲の雰囲気や価値観も、実は日本特有のものである可能性が高いのです。
特に、日本では内向型(I)の割合が高いことが顕著な違いと言えるでしょう。
この違いが生まれる背景には、その国の文化や歴史、社会的な価値観が深く関係していると考えられます。
日本では集団の調和を重んじ、謙虚さや思慮深さが美徳とされる文化が根付いてきました。
こうした国民性が、慎重で計画的な判断型(J)や、現実的で着実な感覚型(S)の割合を高めている一因かもしれません。
具体的には、アメリカではリーダーシップや積極性が重視されるため、ESTJ(幹部型)やENTJ(指揮官型)といった外向型の割合が高い傾向にあります。
一方、日本ではINFP(仲介者型)やISFJ(擁護者型)といった、内省的で他者への配慮を大切にするタイプが上位に来ることが多いのです。
このように、MBTIのタイプ分布からは、その国の文化的な特色を垣間見ることができます。
日本人と世界のMBTIの割合
日本におけるMBTIタイプの割合は、世界と比較して非常に興味深い傾向を示します。例えば、ある有名な性格診断サイトの2023年の国別データによると、日本では「仲介者型」INFP-Tが16.46%と最も多い結果でした。これに「運動家型」ENFPや「擁護者型」ISFJが続くことから、内向型(I)や感情型(F)のタイプが比較的多いという特徴が見て取れるでしょう。一方で、世界に目を向けると様相は大きく異なります。アメリカでは「管理者型」ISTJが最も一般的とされ、世界全体でも「番人」気質(SJ型)や外向型(E)の割合が高い傾向にあるのです。こうした違いには、集団の調和を大切にする日本の文化的背景が、個人の性格形成に影響を及ぼしている可能性が考えられます。
日本文化がMBTIに与える影響
日本の社会が持つ集団主義的な価値観は、MBTIの診断結果に影響を与えていると考えられます。例えば、聖徳太子が十七条憲法で説いた「和を以て貴しとなす」という精神は、他者への配慮を優先するF(感情)タイプや、協調性を重んじるJ(判断)タイプの傾向を強める一因となっているかもしれません。自己主張よりも周囲との調和を美徳とする文化が、個人の性格形成に作用するのでしょう。
また、「出る杭は打たれる」といった言葉に代表されるように、謙遜が重んじられる風潮も存在します。これにより、自己の内面と向き合うことを得意とするI(内向)タイプと自己認識する人が多くなるのは、自然な流れではないでしょうか。さらに、かつての終身雇用制度が象徴するように、変化よりも安定を好む国民性は、現実的で着実なS(感覚)タイプや計画的なJ(判断)タイプの気質と親和性が高いといえます。これらの文化的背景が複合的に絡み合い、日本人にISFJ(擁護者型)のような特定のタイプが多く見られる傾向を生んでいる可能性があります。
MBTIに関するよくある質問
MBTI診断を試したあと、「この結果は本当に自分に合っているのか」「もっと詳しく知りたい」など、さまざまな疑問が浮かんでくる方もいるのではないでしょうか。
自分の性格タイプがわかると、嬉しさや納得感がある一方で、新たな悩みや関心が生まれるのはとても自然なことです。
その理由は、MBTIが単なる性格分類ではなく、自己理解を深めるための「きっかけ」となるツールだからでしょう。
そのため、診断結果の信頼性や、他のタイプとの相性、仕事への活かし方など、より実践的な側面について知りたくなる気持ちが湧いてくるのです。
特に日本では多くの人が関心を持っており、情報交換も活発に行われています。
具体的には、「診断結果は一生変わらないの?」や「特定のタイプとの相性はどうなの?」といった質問がよく寄せられます。
人の性格は成長や環境の変化によって成熟していくため、診断結果が変わることは十分にあり得ます。
また、相性もあくまで参考情報の一つであり、コミュニケーション次第で良好な関係を築くことはもちろん可能である、という点が重要です。
日本で人気のMBTIタイプは?
日本で人気のMBTIタイプに関して、公式な統計データはないものの、各種調査から一定の傾向がうかがえます。株式会社テスティーが2022年に実施した調査では、最も多いタイプはINFP(仲介者型)で、全体の14.5%を占めるという結果が出ました。感受性が豊かで理想を追求するINFPが1位というのは、非常に興味深い点でしょう。続いて多かったのは、情熱的で社交的なENFP(広報運動家型)で12.5%でした。
これらの調査とは別に、伝統的に日本人に多いとされてきたのがISFJ(擁護者型)です。ISFJは献身的で周りへの配慮を欠かさないため、和を重んじる日本の文化に馴染みやすい性質を持つと考えられます。また、実直で責任感の強いISTJ(管理者型)も、多くの組織で堅実な働きぶりが評価されるタイプといえるでしょう。これらの結果はあくまで一例ですが、自己理解を深める面白い指標となります。
MBTI診断で就職活動に役立つのか?
MBTI診断は、就職活動における自己分析の強力なツールとして活用できます。診断結果は自身の強みや価値観を言語化する手助けとなり、エントリーシートや面接で一貫性のある自己PRを構築するのに役立つでしょう。例えば、「思考型(T)」の結果が出たなら、論理的思考力を活かせる職務への適性を具体的に示す材料になります。実際に、一部のIT企業やコンサルティングファームでは、採用選考の参考資料や入社後のチームビルディングの材料としてMBTIを用いるケースも存在します。しかし、診断結果はあくまで性格の傾向を示す参考指標であり、個人の能力や将来の可能性を決定づけるものではありません。適職診断の結果に固執しすぎず、多角的な自己分析の一環として捉える姿勢が大切です。診断は、自分をより深く理解するためのきっかけと考えるのが賢明でしょう。
まとめ:【MBTI】日本人に多い性格を知って自己理解を深めよう
今回は、日本人のMBTIの傾向について関心がある方に向け、
– 日本人に多い性格タイプランキング
– 各タイプの詳しい特徴
– MBTI診断を生活に活かすヒント
上記について、解説してきました。
調査結果からも分かるように、日本人の性格タイプには一定の傾向が見られます。
これは、日本の文化や社会的な背景が、私たちの性格形成に影響を与えているからでしょう。
ご自身のタイプがランキングのどの位置にあるか、気になった方もいるかもしれませんね。
このランキング結果は、単に多数派や少数派を知るためだけのものではありません。
自分と他者の考え方や感じ方の違いを理解する、素晴らしいきっかけになるのです。
これまで自分の性格について深く考えたり、人間関係で悩んだりした経験は、決して無駄ではありませんでした。
MBTIは、そうした経験に「なぜだろう?」という問いへのヒントを与えてくれる、ひとつの便利な道具です。
ご自身の性格タイプが持つ独自の強みや魅力を知ることで、今後の人生がより豊かなものになるでしょう。
自分らしさを大切にしながら、他者と良好な関係を築いていく道筋が見えてくるはずです。
ぜひ今回の内容を参考に、あなたの素晴らしい個性を再発見し、日々の生活や仕事に活かしてみてください。
筆者は、MBTIというツールを通じて、毎日がさらに輝くことを心から応援しています。